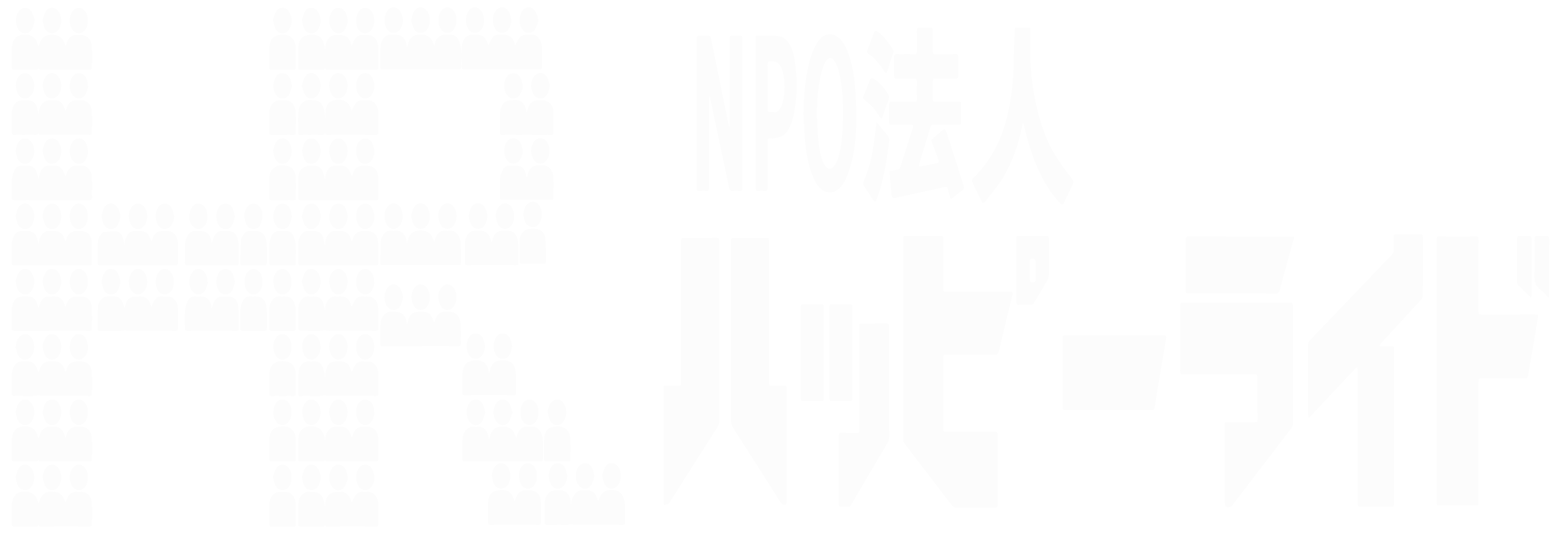「72時間を生き残れ!避難所体験ごっこ」実施レポート
――“できない”は個人の問題じゃない。みんなで生き残るためのヒントだ。
半年かけて準備してきた企画、
「72時間を生き残れ!避難所サバイバル診断 in 避難所体験ごっこ」が、無事に終了しました。
この取り組みに関わってくださった皆さんへ、
まずは心からのお礼を伝えさせてください。
当日集まってくれた障害当事者13人のみなさん。
別府公民館の職員の皆様、歴代館長。
別府校区自治協の会長、人権尊重協議会の皆さん。
NOLIMITのみなさん、点字図書館館長。
防災YouTuberたこちゃん。
お休みにもかかわらず参加してくださった行政職員の皆様。
そして、打ち合わせの段階から伴走してくださった博多あんあんリーダー会の皆様。
この場を一緒に作ってくれて、本当にありがとうございました。
「できない」は、その人のせいじゃない。
この半年間ずっと考えてきたのは、
「どうしたら“避難をあきらめている人”の現実に、本気で向き合えるのか」
ということと
「避難する事が当たり前の人にどう伝えたらいいのか?」の両面でした。
段差があるから移動できない。
文字が見えないから様々な情報が取れない。
トイレの場所がわからない、それだけではなくトイレットペーパーの位置がわからない
ついつい使い方が不安で我慢してしまう。
声をかけると申し訳ない空気があって「助けて」が言えない。
そんな課題が避難所にはあります。
こうした“できない”は、その人の努力不足でも、わがままでもありません。
それは環境やルール、設計側の問題と定義したんです。
だから大事なのは、「できないこと」を隠さないこと。
遠慮せずに出してもらい、みんなで集めて、「どうやったら一緒に生き延びられるか?」と考え続けること。
だからこそ、
最初にみんなで体験して同じ目線で「できないこと」を集めて課題の顕在化をすることが大事。
次に困りごとを正直に書き出してもらい、「じゃあどうしたら一緒に生き延びられる?」と防災士や地域を作る人、人権尊重協議会、女性視点など様々な観点で考えアイディアを出し続けることこそが、
私たちのいう「事前防災」であり、「地域レジリエンス」の一歩だと感じています。 地域全体でしなやかに備える「地域レジリエンス」につながる一歩だと思っています。
地域全体でしなやかに備える「地域レジリエンス」につながる一歩だと思っています。
「ここは安心な場所なんだ」と思えた夜
正直に言うと、参加してくれた障害当事者のみんなは、
知らない人たちとの“プチ共生体験”で、きっと緊張したり、
眠れなくなったりするかもしれない――そう想像していました。
でも、実際にフタを開けてみると。
発達障がいの子が司会者の前でのびのびと自己表現をして、
ダウン症の子も、視覚障がいの参加者も、
周りのみなさんの受け入れのおかげで、
きっと本能的に感じていたはずです。
**「ここは本当に“安心な場所”なんだ」**と。
だからでしょうね。
終始ご機嫌で、たくさんの笑顔があふれていました。
そして象徴的だったのが、視覚障がい当事者お二人の警戒レベルの「いびき」です。
まるで「ゴジラ対メカゴジラ」のように響き渡る、豪快ないびきバトル (笑)
何が言いたいかというと――
それだけ不安なく、ストレスなく、“ぐっすり眠れた”ということ。
避難所で「安心して眠れる」というのは、当たり前のようでいて、実はとてもハードルが高いことです。
その一歩を、この場で一緒に体感できたことが、何よりうれしかったポイントでした。
「最高の避難体験」がくれた宿題
今回の避難体験・避難宿泊体験は、
ただ楽しかった、いい経験だった、で終わるものではありません。
・できないことを言葉にしてもいい空気があるか。
・それを一緒に考えてくれる人や仕組みがあるか。
・当事者が「迷惑」ではなく「仲間」として扱われているか。
この日、別府公民館で生まれた光景は、
「こういう避難所なら、避難をあきらめていた人も来られる」という、一つのモデルケースでした。
今日出てきた“できない”“困りごと”は、誰かを責める材料ではなく、
地域でルールや導線、声かけ、情報提供のあり方をアップデートしていくための、大切なヒントです。
この場に関わってくださったすべての皆さんへ、あらためて感謝を。
そしてここから先も、
「遠慮せずに困りごとを言える避難所」
「一緒に考えてくれる仲間がいる地域」
を、共に育てていけたらと思います。
#72時間を生き残れ #避難所サバイバル診断 #事前防災 #地域レジリエンス #共感型支援 #ご近助ネットワーク #インクルーシブ避難所